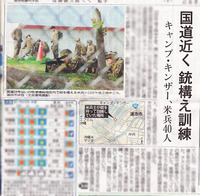2010年08月07日
続「アメとムチ」の構図 ~砂上の辺野古回帰~⑭
国の切り崩し工作
地元区に「生活補償」 要求決議に影響も
辺野古区の容認決議の本質は「最大限の生活補償」に向けた条件闘争だ。同区が政府に対し、容認の条件に「生活補償」を挙げるのは常とう手段といってもよい。
2006年4月7日の防衛庁長官額賀福志郎と名護市長島袋吉和の「V字案」での基本合意から10日後の同月17日。辺野古区は行政委員会を開き、同案の沖合移動とともに、1世帯当たり1億5000万円の一時金と毎年200万円の永代補償など22項目の地域振興事業を政府に要求することを決議した。
この際、移設に反対する区民から「賛成と受け取られかねない」と問いただされた区長大城康昌は、「移設を強行された場合の担保になる」と突っぱねた。
ところが、5日後の22日に区長や行政委員らが防衛施設庁に要請した時点で、具体的な補償金額は明記されなかった。事前調整で政府が難色を示したためだ。
前日21日の衆院安全保障委員会では、外務副大臣塩崎恭久が「ODA(政府開発援助)もそうだが、自らの足で立って自ら頑張るのが基本だ」と答弁。質問した沖縄選出の衆院議員下地幹郎にも「(辺野古区などの補償要求を)絶対にのんじゃいけない。こういうことをやると沖縄は良くならない」と言われる始末だった。
辺野古区は04年にも1億5000万円の一時補償を政府に要求している。
ただ、06年4月の同区の個人補償要求決議には、別の伏線もある。
V字案の前身である沿岸案(L字型案)が05年10月に日米で合意されたものの、県や市、地元区はこぞって反対した。そこで防衛省は、沖縄側を切り崩す取っかかりとして久辺3区に狙いを定め、説得工作を展開した。
「地元の振興のために何でもする。受け入れてくれ」。辺野古区出身の市議島袋権勇は、上京時に防衛事務次官守屋武昌からそう持ち掛けられた。
06年2月、那覇防衛施設局長に赴任して間もない佐藤勉は、守屋から個人補償をちらつかせる地元説得の「口説き文句」を伝授されている。
(1)SACO振興策で久辺3区が潤ったか。雇用面を見ても名護市の西海岸が主体。従前から西海岸にだけ目が向けられていた
(2)安全と生活面の改善の観点から久辺3区に特化した町づくりをお手伝いしたい
(3)町づくり以外にも何かできることはないか、腹を割って話したい。例えば個人補償も聞くがどうか―といった具合に、佐藤の備忘録には段階ごとに分けられた具体的なセリフ回しが詳細につづられている。
辺野古区の個人補償要求決議は、こうした政府の揺さぶりが作用した可能性も否めない。(肩書は当時、敬称略)
(続「アメとムチ」取材班)
Posted by ミチさん at 16:41│Comments(0)
│反基地