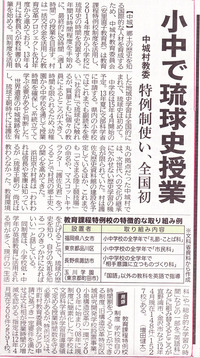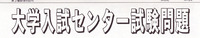2010年04月10日
沖縄密約全面勝訴
[沖縄密約全面勝訴]知る権利が尊重された
明快で常識にかなった判決だ。機密度の高い外交文書が一方の国にあって他方の国にないのは考えられない。存在しない場合は廃棄したとみたほうが筋が通る。廃棄に至る具体的な状況は、歴代事務次官ら幹部を聴取すれば分かるはずであり、それなしでは十分な調査とは認められない。
1972年の沖縄返還をめぐり米軍用地の原状回復費用を日本政府が肩代わりした文書などの開示を国に求めた訴訟で、東京地裁の杉原則彦裁判長は関連文書の全面開示を命じた。国家賠償も認め、原告側の全面勝訴の判決となった。外務省有識者委員会や財務省に続き、司法としても密約の存在を認めた。
判決は原告の訴えを「密約の存在を否定し続けた政府の姿勢の変更を求めるものであり、民主主義国家における国民の知る権利の実現だった」と正面からとらえ、自民党政権時代の国の対応を「国民の知る権利をないがしろにした不誠実なものといわざるを得ない」と厳しく批判した。
原告は当時、密約をスクープした元毎日新聞記者西山太吉さん(78)をはじめとする県内外の研究者ら25人。2009年3月に提訴した。
開示を求めていたのは(1)軍用地の原状回復費用400万ドルの日本側肩代わり(2)海外向け短波放送中継局(VOA)の国外移転費用1600万ドルの日本側負担(3)返還協定合意の3億2千万ドルをはるかに超える日本側の財政負担―を示す3文書とその関連文書。原告の一人でもある我部政明琉球大教授が米国立公文書館で発掘した文書ばかりである。
3密約文書は同じ構図をとる。400万ドルと1600万ドルについて吉野文六・元外務省アメリカ局長(91)は審理で、自身がイニシャルでサインしたと証言した。その時点で写しを取らせており、東京地裁は文書を保有していたと判断した。文書発見の調査は国の機械的、事務的な方法では困難としながら、「国が現在も保有していない証拠はない」との見方を示した。政権交代前に密約を否定していた立場の者が探したとしても「その精度、結果の信用性には限界がある」からだ。
文書は、すでに廃棄された可能性もある。もし廃棄されているのなら、外務省の相当高い地位の者がかかわって組織的に意思決定していたとしか考えられないと言及した。判決は、国に歴代事務次官の聴取など再調査を求め、文書が「不存在」の場合は、立証責任も負わせた形だ。論理展開は説得力がある。
「記録なくして歴史なし」といわれる。公文書の公開度は民主的な国かどうかを測る物差しだ。外交交渉の検証は現在、そして未来に向けた政策の指針となり、交渉当事者は歴史の審判に向き合うことを自覚せざるを得なくなる。
自民党政権時代の国の姿勢は極めて不誠実だった。実務責任者がサインを交わしたと認めた後も、密約を否定する姿勢を崩さず、公然とうそをつき通した。代償は国に対する不信感となって跳ね返ってくる。判決で国は公文書公開と管理のあり方も厳しく問われたと受け止めるべきだ。
Posted by ミチさん at 19:54│Comments(0)
│沖縄史